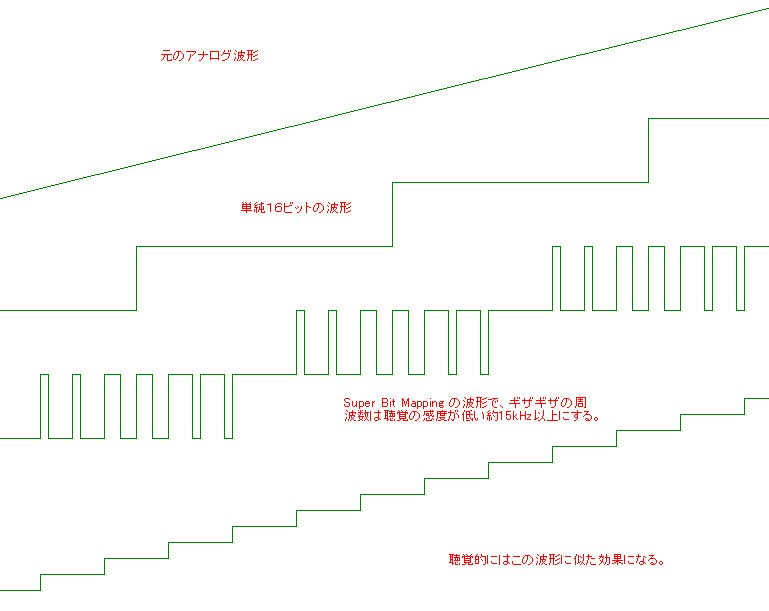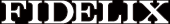
 アナログ約60dB、デジタル90dB以上というDレンジは比較不可(その2) アナログ約60dB、デジタル90dB以上というDレンジは比較不可(その2) |
中川 伸 |
|---|
アナログ約60dB、デジタル90dB以上というDレンジは比較不可、の中におけるアナログとは2トラック38cmのオープンテープを想定しています。ではLPはどうかといえば、このDレンジがそっくりそのまま入ります。アナログ録音のレコードに針を落とすと、先ずはレコード溝の摩擦音が小さく出ます。次にテープのヒスノイズが聴こえ、その後にテープ転写のゴーストが聴こえ、それから本来の音楽が聞こえます。ですから、テープを使わないダイレクトカッティングはDレンジが上がるのです。
私はソニーのTC-D5MやPCM-D50で生録を時々しますが、仲間の何人かは「DレンジはDATの足元にも及ばないんだけどね、、。」と言いながら、私が憧れているナグラのオープンリールを回したりしています。きっと音は気に入っているのでしょう。それでCD初期のDレンジの上げ底表示をそのまま信じている人たちがまだいることが分かり、私はエンジニアとして、これは放っておけないと素直に思いました。
最初にデジタル録音を始めたのはNHK技研で、1967年のことですが、ここと関係の深かった日本コロンビア(現デノン)はPCM録音(44.1kHzで13ビット)を1974年に始めました。早稲田大学の山崎芳男氏やソニーも研究を始め、ソニーは1977年にPCM-1というVTRへの録音機を発売しました。この頃に、フィリップスはデジタル信号を光ディスクに記録する方法を考案し、ソニーのPCM技術とフィリップスの光ディスク技術が手を組んで生まれたのがCDです。当初のフィリップス案は直径11.5cmで14ビットの60分でしたが、ソニーは16ビットを主張し、カラヤンはベートーベンの合唱が収録できるよう74分を望みました。そこで、16ビットで74分にするため、12cmに増えました。この16ビットにしたことが後に出現するパソコンと非常に親和性が良く、データー用としても広く使われることになります。
さて、オーディオ業界では1980年頃はパッとせず、何でも良いからヒット商品がほしかった時期なので、このCDに期待をしました。アナログとCDのDレンジは、性格が異なるので簡単な比較はできなくて、計算方法によっても色々な結果が出ました。しかし、業界としては、夢のオーディオということで売り出したかったので、測定方法や表示方法も業界団体であるEIAJである日本電子機械工業会(現在はJEITAである電子情報技術産業協会)によって変更を加えました。CDにはいくつか下駄を履かせた測定法を採用することで、圧倒的に優れているとして売り出しました。
雑誌社もCDの音はさほどでもないという意見があることを知りつつも、CDは生まれたばかりの赤子なので応援するという立場を取りました。そのため、普及するまでの期間は、否定的な意見は雑誌に殆ど載りませんでした。こうしてCDはアナログを駆逐するほどに大成功を収めました。今にして思えば、CDが利便性においてオーディオに多大な貢献をしたことは確かです。
CDの当初の売り出し文句が額面通りなら、以降の改良技術は不要ですが、そんなことは無かったのでいろんな新技術が次々に開発されました。最初は量子化ノイズの規則性を無くすため、ディザ(実態はノイズですがこのような呼び方をした)を加えることで規則性を分散させました。デノンのPCM録音LPも、カッティング時にはスチューダーのテープレコーダーを通すことで、ヒスノイズによるディザを加えていた時期がありました(スペアナで計れば分かるかも知れません)。さて、最初のディザは±1LSB〜±3LSB程度の小振幅ディザでしたが、後に大振幅ディザへと発展してゆきます。大振幅ディザは大きめのディザを加えてDACを通し、あとからディザ成分を引き算することで、DACの段(LSB)の不規則性を改善するものです。マルチビット型DACはバラツキにより、段は不規則になりますが、この改善方法の一種です。他にDACを選別したり、並列接続によるバラツキの平均化や、DAC内ネットワークのレーザートリミングやなどでDACの制度を上げる方法が取られました。
オーバーサンプリングという技術がフィリップスで開発され、当時フィリップスグループだったマランツブランドから1985年にCD-34が発売されました。これは20kHz以上をカットする急峻なフィルターによる弊害が出ないよう、なだらかなフィルターが使えるようにしたものです。
また、基本的に、段の揃った1ビット系のDACでは、例えばビットストリーム(フィリップス)やMASH(パナソニック)や、他にDDコンバーター(ビクター)などがあります。しかし、16ビットからさらに段を細かくするには、中間の値を作りだし、より細かなギザギザにしなくてはなりません。そこで、ビットを拡張する技術が始まりました。
最初に始めたのはデノンのALPHAプロセッシングですが、13ビットで画期的とPCM録音を始めた会社が、16ビットでも不足として20ビット以上にまで拡張を始めたことはなんとも興味深いです。その後に、20ビットK2プロセッシング(ビクター)、Pro Bit(ヤマハ)、DRIVE(ケンウッド)などが出現しますが、これらの技術は、無線と実験の2008年7月号〜2009年11月号で柴崎功氏によって詳細な解説がなされていますので、感心のある方はぜひともこちらをご覧になって下さい。このALPHAプロセッシングから始まったビット拡張技術は、とにかく聴きやすくなるので、私にとってはいずれもが好ましいと感じています。
ではソフトの側で16ビットのままでもそれ以上の効果を出せる方法として、ソニーが開発したSBM(スーパービットマッピング)というのがあります。20ビット以上の信号でも16ビットに入れる方法ですが、私がわかりやすいよう、ここでは2ビット分の拡張を想定して図にしました。この音の違いは別なページからサンプルをダウンロードして比較試聴できますが、PCM-D50で96kHzの24ビット録音したものを、CDに収録する際に、単純に16ビット44.1kHzにしたものと、SBMを使って16ビット44.1kHzにしたものです。これを音楽CDとして焼けば、オーディオ装置で聴き比べができます。この2つのチャルダッシュを聴くとSBMはなかなか優れた技術であることが分かると思います。勿論、96kHzの24ビットのオリジナルに近くなります。20ビット以上の信号を16ビットに入れる方法は、この他に、デノンのトランスクォンタイザーや、ビクターの20ビットK2スーパーコーディングがあります。
今ではPCM-D50などで安く簡単に96kHz24ビット録音までなら可能なので、聴き比べれば16ビットで十分だとか、44.1kHzで十分だという意見はどちらも間違いであったことが即座に分かります。
結局のところ別なページでも書いていますがローレベルが如何に重要であるかに尽きると思います。私が部品や回路にこだわっているのは、測定では出にくい微小レベルの再現性を重視しているからで、このことによって臨場感や細やかなニュアンスの再現性が向上します。スイッチング電源のノイズを世界最小クラスにしたのもこのローレベルの再現性を重視したからです。
私は高音に敏感で、ピアニッシモにも敏感なので、初期のCDや初期のデジタル録音LPは、数分間聴くだけでも頭が痛くなるので、とても聴く気がしませんでした。そんな私でも最近の優秀録音のCDなら聴けるまでに進歩してきているのは事実です。でも、ヴァイオリンやソプラノは、まだハーモネーターを使わないと長時間は聴けません。次回はこういった超高域の付加技術やHDCD、DVDオーディオ、SACDについて書くことにします。